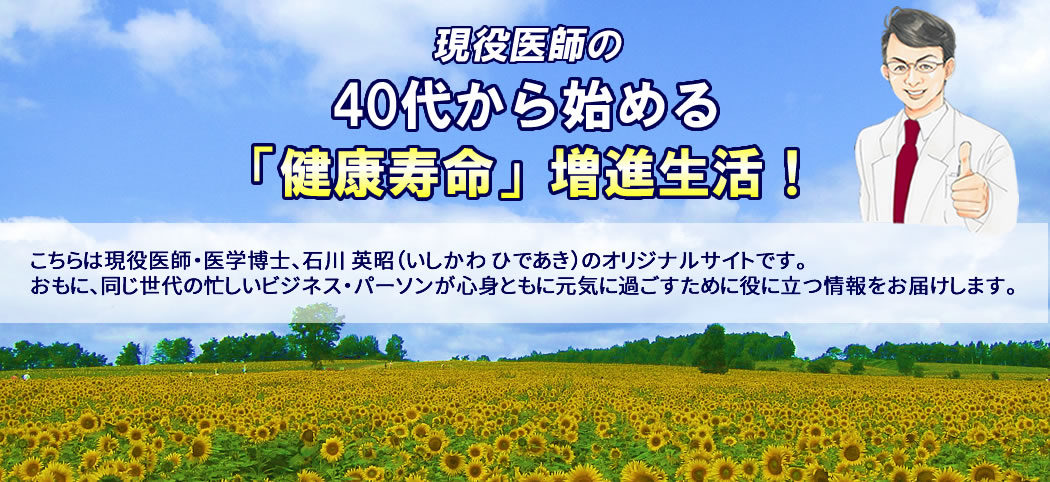私のプロフィールにもあります通り、
ご先祖様は、直参旗本(じきさんはたもと)として、
江戸時代を通して、徳川幕府にお仕えしておりました。
そして、旗本家臣団であった石川家の一部のご先祖様は
「江戸屋敷詰」の家老以下三十余家の譜代の家臣諸家
※柴田 知憲氏著
旗本大嶋石川氏(家禄七千石)の家臣団-文化年間(1804-17)以降を中心により引用
と江戸屋敷、つまりは、江戸に住居を構えていた事になります。
では、いったいそれは、どのあたりなのだろうか?
今は、どのようになっているのだろうか??
末裔としては、
当然この事に興味が向かう訳であります。

※石川家の上屋敷は、江戸のどのあたり??であったのか。
そして、柳営会入会のご相談依頼、親しくさせて頂いている
先の柴田さんより、
貴重な御本とともに、その所在を特定する事が出来ました!
また、こうした過去の史料と同じくして、
スマートフォンのアプリ
「大江戸今昔めぐり」
※外部のサイトにリンクします。
でも、同様な結果が得られました。
まずは、古地図のお写真からお見せ致します。
※クリックで拡大します。
地図上、赤い矢印をご覧下さい。
石川 祥作 の文字が確認できるかと思います。
水道橋のすぐそば、
道を挟んで、水戸殿と書かれており、
水戸藩のお屋敷があった事もこれで分かります。
水戸藩邸は、今は小石川後楽園として、その上屋敷の面影を
偲ぶ事が出来ますね。
https://www.tokyo-park.or.jp/park/format/about030.html
※小石川後楽園のサイトにリンクします。
石川 祥作公の、祥作は、通称・官位名であり
伊豫守(いよのかみ)、阿波守(あわのかみ)であらせられた
大嶋石川家 第九代 御当主
石川 總邦(ソウハン ?)公である事が、柴田氏の御著書より判明しています。
總邦公が生きておられた時代は、
天保年間(1831年から1845年までの期間)との事です。
天保と言えば、歴史でも勉強した
「天保の改革」がもっとも有名な出来事ですよね。
※Wikipediaのサイトにリンクします。
またこの時代、
※Wikipediaのサイトにリンクします。
であったようです。
そして石川 總邦公は、幕府の役職として
※Wikipediaのサイトにリンクします。
の重責を担われていたようです。
通常より高い火力を有した銃を装備し、江戸城の城門を警備していた
訓練された精鋭の戦闘集団であった百人組。
抱席・二十五騎組、伊賀組、譜代席・根来組、甲賀組の4組からなり、各組に100人ずつの鉄砲足軽が配された。組頭は、その鉄砲隊の頭領である。
しかも、その構成要因には、伊賀組、甲賀組などの名前が!!
伊賀組については、
とあり、江戸城を守っていたのは、なんと忍者部隊であったのか!
などと、興奮してしまいますね。

そして、彼らの頭領こそが、
我がご先祖様、石川 總邦公。。。
なんだか、とても痺れます笑!
こちらの記事にも書きましたが、
ご先祖様は、やはり江戸幕府をお守りする、
いざとなったら戦いに命を差し出す、
侍
であったんだな、と実感する次第です。
そして、もうひとつ。
先のアプリで、この辺りの江戸時代の地図を検索してみました。
※クリックで拡大します。
こちらの地図では、同じ場所に、
石川 總登(ソウト?)公の文字が読み取れます。
總登公は、
第八代、大嶋石川家御当主、つまりは 石川 總邦公の
先代にあたる関係になるようです。
總登公、については、また改めて書いてみたいと思っています。
最後に、今現在、水道橋駅前の交差点の地点に該当しており
※外部のサイトへリンクします。
もし、明治維新がなく、今も江戸幕府が続いていたならば、
私も、この辺りに住んでいたのかな?
などと妄想する事は、ワクワクします。
お読みいただき、ありがとうございました!!